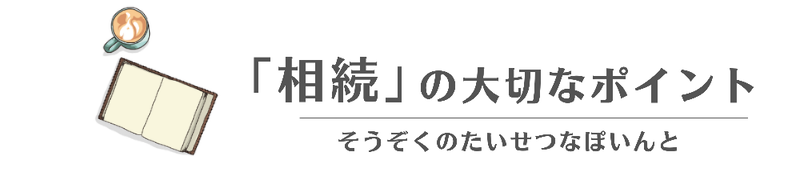贈与税についての
対応方法
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
贈与税に関しては、いくつかのルールがあります。それらの内容に関して、わかりやすく説明しています。

暦年課税とは、
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税
という方式です。
つまり、その年の贈与税を、都度、計算して税金を納めるというものです。
相続時精算課税とは、
一定の条件のなかで、贈与時の「贈与税」を非課税にするかわりに、相続時に、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税する
という方式です。
相続時精算課税の場合、
節税ではなく、単に、税金の先送りができる
という内容になっています。
それぞれの内容と、注意点について、説明します。
暦年課税について

暦年課税の場合、
年間の非課税枠は、110万円
となっています。
また、
贈与時の制限(贈与する側の年齢や、対象者等)
もありません。
年間の非課税枠(110万円)の範囲であれば、申告の必要もありません。
暦年課税の注意点 ~定期贈与について~
暦年課税の注意点としては、定期贈与に関する事項があります。
相続が起きた時からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、相続税課税の対象になります。
※2024年1月1日から適用される税制改正により、「3年以内→7年以内」に変更になります。
暦年課税の計算方法
暦年課税の計算方法としては、下記になります。
暦年課税 = 課税価格 ー 基礎控除額(110万円)
課税額は、
控除後の課税額 × 税率 ー 外国税控除額
の計算式で算出します。
贈与税の配偶者控除額(最高2000万円)について
贈与税の配偶者控除とは、配偶者から、
住居用の不動産
または、
住居用の不動産の購入資金
を贈与された場合、
最高2,000万円まで
が控除できる制度です。
配偶者については、下記の条件を満たせば、贈与額に関して、
最高2000万円の控除額
あります。
・婚姻期間が20年以上である
・国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつその後も継続して居住する見込みであるもの
また、この制度は、
1度しか適応できない
という注意点があります。
備考;贈与税の対象外となるもの
下記は、贈与税の対象外となります。
・冠婚葬祭費
・扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金や教育資金のうち一定の要件を満たすもの・法人からの贈与(贈与税ではなく、所得税の対象となります)
等
また、詳細は、下記の国税庁のページに記載があります。
相続時精算課税

相続時精算課税とは、前述しましたように、
一定の条件のなかで、贈与時の「贈与税」を非課税にするかわりに、相続時に、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税する
という制度になります。
また、この制度は、
その対象者や要件
に一定のルールがあります。
下記に順に説明します。
相続時精算課税の対象
贈与する側の年齢と続柄に関して、
贈与年の1月1日に、60歳以上の親、祖父母
となっています。
また、贈与を受ける側については、
贈与年の1月1日に、18歳以上の子(または代襲相続人)
となっています。
控除額について
控除額は、贈与者ごとに、
2,500万円まで
となっています。
また、複数年度になる場合は、
累計額が2,500万円まで
となっています。
申告について
相続時精算課税を適応して際には、
贈与を受けた翌年の2月15日~3月15日
の間に、所轄の税務署に申告を行う必要があります。
注意点
相続時精算課税の注意点としては、下記があります。
・相続時精算課税の申告をした場合は、相続開始まで適応となります。
ですので、途中で取り下げができないということになります。
・上記の結果、
贈与税の年間110万円の控除の対象外
となります。
但し、令和5年度税制改正で、「基礎控除」が創設され、
年間110万円までの相続時精算課税贈与は、相続財産に加算されない
ということになりました。
(令和6年1月1日以後に贈与に適応)
相続時精算課税の範囲を超えた分に関して
相続時精算課税の2500万円を超えた分に関しては、
一律20%の税率
となります。
※補足
相続時精算課税の対象となる場合の相続に関しては、
贈与財産の累計額を、相続財産に合算して計算する
ということになります。
その際、既にしはらっている贈与税があれば、それを差し引いて相続税額を計算します。
その結果、払いすぎがあれば、還付請求することができます。
まとめ

贈与税に関しては、一般的には、
暦年課税
となります。
ただ、相続との関係で、
相続時精算課税
を選択する場合もあります。
それぞれ、メリット、デメリットがありますので、どの方法がいいのか、税務の専門家である税理士さんと相談されることをお勧めします。
また、税理士さんの中にも、相続税が得意た方と、そうでもない方がおられますので、注意しましょう。
以上、贈与税の計算についての説明でした。